古文書解読検定は協会自体できたばかりで2016年7月に第1回検定が行われました。
いままで古文書に関する資格はNHK学園の生涯学習インストラクター(古文書)しかなかったので、古文書解読技能の腕試しをしてみたい、漢字検定や英語検定のような古文書の資格があればなぁと思っていた人にとっては喜ばしいことではないでしょうか。
かくいう私もその内の1人で第2回検定を受検してみました。
現時点でまだ結果が郵送されていないので、古文書解読検定がどのようなものかご紹介ると共に合格体験記として進級していく様子を綴っていこうと思います。
◎古文書解読検定とは?
古文書解読検定ホームページ
古文書解読技能の実力を測ること、またその技能に対し社会的ステータスを付与することができる検定です。
〈試験実施日〉
検定は年2回実施されており、7月と1月に行われています。
〈受験級〉
受検級は必ず全員3級からスタートしなければなりません。ここが漢字検定や英語検定のような好きな級から受検できる検定と大きな違いです。
大学教授も博物館の研究員でも実力に関係なくみんな3級からスタートです。
〈試験内容・合格基準・検定料〉
《試験形式》
郵送試験 3級・準2級・2級 問題発送→解読文を返送→郵送で合否・総合順位の通知
会場試験 準1級・1級 受験票を持参し、指定会場で実施
《受検料と合格基準の目安》 受検料は消費税込みです
3級 4000円 全受検者の上位8割以上の成績
準2級 5000円 上位7割以上
2級 6000円 上位6割以上
準1級 8000円 上位5割以上
1級 9000円 上位3割以上
※合格基準は一応の目安で多少前後することがあります。
合格基準についても漢字検定が〇割で合格のように、絶対評価なのに対して古文書解読検定は相対評価と少し変わっています。
検定料についてですが、1級まですべて取得するのに3万2千円の費用がかかります。
自信のある人にとっては現時点で取得できそうな級から受けられず、費用と時間がかかるという点がデメリットではないでしょうか。
公式ホームページには例題もありますので、まずはどのようなものか体感してみてはいかがでしょうか。
(追記)
30歳以下の方は受験料が安くなるとの発表がありました!!
詳しくは以下の記事をご覧ください。
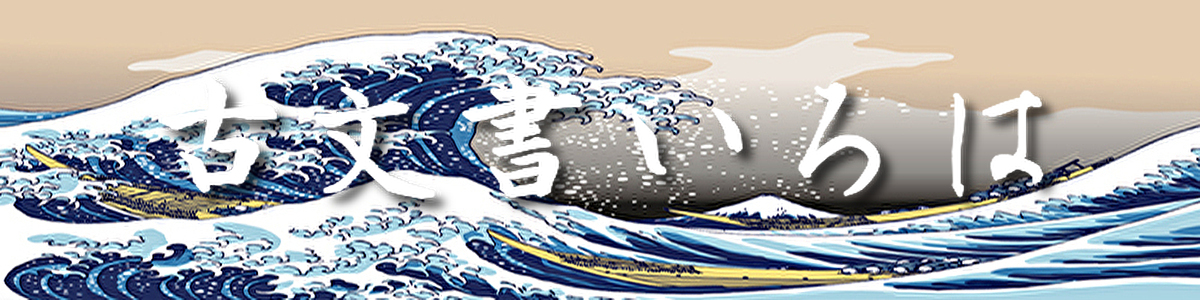

コメント